「今の職場で働き続けるのは難しいかもしれない・・・」
そう感じている生活相談員の方はいませんか?
生活相談員の離職率は5%という数字があります。
(※厚労省のデータの中には生活相談員だけの離職率はありません。転職サイトにあった数字を参考にしたことと、高齢者施設全体の離職率と介護職員の離職率を勘案すると5%という予想ができます。)
毎日、利用者さんのために頑張っている生活相談員は、やりがいがある一方で、責任も大きく、心身ともに負担を感じることが多いと思います。退職という決断は、決して簡単なものではありません。
退職を決断する前にもう一度現在の状況を振り返り、本当に退職してよいのか、感情的になっていないかを考え直す必要があります。
しかし、もしあなたが本当に今の職場で限界を感じているなら、無理に続けることが必ずしも良いとは限りません。
そこでこの記事では、生活相談員が退職を考える主な理由と、退職を決断する前に考えてもらいたいこと、そして後悔しない円満退職をするために知っておくべきことを、具体的な事例を交えながら解説します。
この記事を読むことで生活相談員が退職を考えるリアルな理由を知り、自分の置かれた状況と比較することができます。
また、退職理由を正確かつ円満に伝えるための具体的な方法が分かります。
さらに後悔のない転職、再就職に向けて、気持ちを整理できます。
ぜひ最後まで読んで、あなたの今後のキャリアについて考えるきっかけにしてください
生活相談員が退職を考える主な理由
生活相談員が退職を考える理由は多岐にわたりますが、ここでは特に多く聞かれる理由を5つご紹介します。
上司(施設長)との考え方の違い
生活相談員の退職の理由で一番多いのが、上司との考えの違いです。介護観の違いも含まれます。
生活相談員が利用者のためを思って行った介護も、上司からしたら経費がかかったり、他の職員のことを考えて、厳しく指導することがあります。
相談員の仕事を教えてもらえない
生活相談員は基本的に施設に1人です。(介護保険法の介護老人福祉施設の基準で100人に1人配置というのが決まっているため)
前任者の生活相談員が辞めたり、他施設へ異動することにより、新しく生活相談員が選任されます。
そのときに、しっかり引き継ぎが行われず、中途半端な状態で仕事を1人で任されることになり、業務に対する不安と施設に対する不信感を募らせることになります。
そういった不安と不信感が解消されることなく、継続して勤務をすると精神的な苦痛がさらに大きくなります。
特別養護老人ホームで介護職員として働いていたBさん。長年生活相談員をされていた方が退職することになり、次の相談員としてBさんに白羽の矢が立ったのです。引き継ぎの期間が1ヶ月半しかなく、分からないことが多い中必死でメモをとり、業務が滞らないように、書類の作成や利用者との面談をがんばりました。しかし、1ヶ月半で教えてもらえることは限られています。感染症などの対応はどのようにしていいか全く分らず、他の職員や施設長も生活相談員の業務を把握していないため、誰も教えてくれなかったのです。心身ともに疲弊してしまい、退職を決め半年後に他の施設に転職しました。
給与・待遇への不満
業務内容の責任や負担が大きい一方で、給与が見合わないと感じる方も少なくありません。
昇給制度が整っていない、賞与が少ないといった待遇への不満も、退職理由の一つとなります。
入職するときは給与面はある程度妥協して就職しますが、やはり生活を切り詰めて、毎日生活しているとだんだん耐えられなくなってきます。
デイサービスで5年間勤務していたCさんは、利用者さんやご家族からの信頼も厚く、仕事にやりがいを感じていました。しかし、長く働いても給与がほとんど上がらず、賞与もわずか。同年代の他業種で働く友人と比較して、待遇の低さに不満を感じるようになり、給与水準の高い他法人への転職を考え始めました。
職場の人間関係の悩み
これは事例1と同じような理由になりますが、介護職員とのコミュニケーションがうまくいかなかったり、職場の雰囲気が悪かったりすると、大きなストレスになります。
生活相談員はコミュニケーション力が問われます。
利用者や家族、現場の介護職員、ケアマネ等、他にも多くの職種の方とコミュニケーションを取らなければなりません。
そのコミュニケーションが滞ってしまうと、仕事の成果も得られませんし、達成感も得られません。
そんな状態が長く続くと、精神的につらくなり、退職を考えるようになります。
5年間ショートステイの介護職員として働いていたDさん、施設長から相談員に挑戦してみないかと言われ、不安ながらも承諾しショートステイの相談員として勤務することになる。生活相談員としての仕事は初めてだったので、少しの失敗は周りの人も大目に見てくれたが、外部の人(家族やケアマネ)に対する失敗については、厳しく指導される。また、だんだん時間が経つにつれ、施設の職員さんも、「施設の信用に関わってくるので、しっかり伝達をして欲しい」と叱責されることも増えてきた。もともと人と話をするのが得意ではなかったため、コミュニケーション力を要求されると、非常に苦しくなり退職に至った。
業務過多・残業の常態化
介護職員は体力的に大変ではありますが、3交代制や4交代制のため、基本的に時間が来れば、次の勤務者に引き継ぎが可能です。
ところが、生活相談員の場合は施設に1人しかいないため、交代がありません。
極端に言えば、100人の利用者からの仕事を1人で抱え込んでいるようなイメージです。
また亡くなった方がいると、夜中に利用者対応をしなければなりません。
昼も夜も関係なく、利用者や家族の対応を1人で行うというのは、さすがに業務過多でこれが理由で退職を考えてしまいます。
結婚を機に、夜勤のある特別養護老人ホームの介護職からデイサービスの相談員に異動の願いを出したが、空きがないという理由で、特別養護老人ホームの相談員となった。最初は慣れない仕事の中、熱心に取り組みお客さんからの信頼も得てきたが、残業が多い上に夜間トラブルがあれば、すぐに連絡が入って対応を強いられる状況となった。「家族との時間を大切にしたい」という思いから、退職を希望するようになった。
本当に「今」辞めるべきか?一度立ち止まって考えてみる
退職を決意する前に、一度立ち止まって冷静に状況を分析することも重要です。
勢いで退職してしまい、後で「もう少し頑張ればよかった」「別の解決策があったかもしれない」と後悔するケースも少なくありません。
この記事を書いている私自身も、上司との考え方の違いで、勢いよく辞めてしまいましたが、次に就職したところの給与は、前の職場より年収で100万下がってしまいました。
後悔はしていませんが、非常に苦しい生活を強いられることとなったのです。
そんな苦しい思いをしないためにも以下のことを、もう一度冷静に考えてみましょう。
問題解決の余地はないか?
上司や同僚とのコミュニケーション
抱えている不満や悩みを、勇気を出して上司や信頼できる同僚に相談しましたか?
伝え方やタイミングを変えることで、理解を得られたり、状況が改善したりする可能性もあります。
異動や業務内容の調整
現在の部署や業務内容がどうしても合わない場合、法人内で異動の希望を出すことや、業務量の調整願いを出すことは可能でしょうか?
調整願いを出せば、法人側も何かしらの配慮があり、抱えていた悩みを解決できるかもしれません。
同一法人の中に大規模施設や小規模施設など、複数の施設を持っている職場は、給料がそのままで新しい環境で働けるので、相談してみる価値はあると思います
外部機関への相談
職場のハラスメントや労働条件に関する問題であれば、労働基準監督署や専門の相談窓口に相談してみるのも一つの方法です。
外部機関へ相談したために、職場に行きづらくなるかもしれませんが、法律上では相談した側が、不利な立場にならないとされています。
職場を改善するためにも、相談してみるのも一つの方法です。
今の職場で得られるもの、失うもの
職場を辞めるというのは、単純に「仕事に行かなくてよい」というだけではありません。
退職すれば、自分の時間がたくさん得られるのは事実です。
しかし、その裏側には必ず失うものがあります。
経験やスキル、人間関係
今の職場で培ってきた経験やスキル、利用者さんやご家族との関係性は、あなたにとってかけがえのない財産です。
辞めてしまうことで、大切な繋がりを手放すことになります。
安定や福利厚生
新しい職場がすぐに見つかるとは限りませんし、見つかったとしても、今の給料が維持できるわけではありません。
福利厚生や雇用の安定性なども、改めて考慮してみましょう。
一時的な感情に流されていないか?
特定の出来事や一時的な感情の高ぶりで「もう辞めたい」と思っていませんか?
少し時間をおいて冷静になることも大切です。
また信頼できる人に話を聞いてもらうことで、気持ちの整理ができることもあります。
一時的な感情で行動に出てしまい、後でひどく後悔することは、よくある話なので、そうならないようにしましょう。
それでも辞めたい!と思う方
上記の内容とは関係なく、心身の健康が脅かされている場合や、どうやっても改善が見込めない状況であれば、退職は必要な選択です。
しかし、上記のような視点から一度立ち止まって考えることで、より後悔の少ない決断ができるかもしれません。
「この選択で後悔はないか?」そう自分自身に問いかけることを、何度も行ってください。
退職理由を伝える際の注意点
生活相談員の退職を決意したら、次は職場に退職の意思を伝えることになります。
この時、伝え方を間違えてしまうと、職場の人間関係が悪化したり、後々まで影響が残ってしまう可能性もあります。
円満退職のために以下の点に注意しましょう。
できるだけ早く伝える
退職する決意が決まったら、まずその意志を伝えましょう。
一般的には退職する日の1ヶ月から3ヶ月前までに、伝えるのが常識とされています。(退職の手続きとして、社会保険の解約に1ヶ月は必要になるためです)
また、介護施設の人員配置の問題や、業務の引き継ぎをする時間も考慮しなければなりません。
正直かつポジティブな言葉を選ぶ
退職理由は正直に伝えることが大切ですが、職場の批判や不満ばかりを並べるのは避けましょう。
「自身のキャリアプラン」「家族の事情」「体調の変化」など、本当は継続して働きたいがどうしようもないということを伝えます。
なるべくポジティブな言葉を選び、理解を得られるように努めましょう。
「上司がむかつくから」とか、「会社の方針が世間一般からずれている」等を言ってもいいのですが、それが解決したら、また勤務してもらえる?と引き戻される可能性があるので、なるべく触れないようにしましょう。
感謝の気持ちを伝える
在籍中にお世話になったことへの感謝の気持ちを伝えましょう。
退職する理由が少しネガティブな内容であったとしても、途中で感謝の意を伝えられると、責める気持ちが薄らいできます。
お世話になったのにお返しができなくて申し訳ないという気持ちを伝えながら、残された勤務や有給消化についても話し合いましょう。
引き継ぎは丁寧に行う
後任者がスムーズに業務を引き継ぐよう、丁寧に説明を行いましょう。
最後まで責任感を持って仕事に取り組む姿勢を見せることは、円満退職につながります。
また、丁寧に引き継ぎをすることで、これまで育ててもらった事業所への感謝の気持ちを、伝えることにもなります。
書面で退職届を提出する
口頭で退職の意志を伝えた後、正式な手続きとして退職届を提出しましょう。
提出時期や書式については、職場のルールに従ってください。
ここでも、書面には「この度、一身上の都合により、勝手ながら20XX年X月X日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」という文章だけ書いて提出しましょう。
「あいつがムカつく」と書きたいのは分かりますが、円満退職のために書くのは控えましょう。
退職理由の伝え方【例文】
具体的な退職理由と伝え方の例文をいくつかご紹介いたします。
【例文1:キャリアアップの場合】
「施設長、いつもお世話になっております。私事で大変恐縮なのですが、この度、一身上の都合により、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご相談させて頂きました。
在職中は、利用者様やご家族との関わりを通して、生活相談員としての喜びややりがいを深く感じることができました。〇〇様をはじめ、職場の皆様には大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
今後、これまでの経験を活かしつつ、より専門的な知識やスキルを習得できる環境で、ソーシャルワーカーとして更なるキャリアアップを目指したいと考えております。
つきましては、退職までの間、責任を持って業務に取り組み、後任の方への引き継ぎも丁寧に行わせていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。」
例文2:体調不良の場合
「施設長、いつもお世話になっております。私事で大変恐縮なのですが、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご相談させて頂きました。
長らくの間、生活相談員の業務に携わらせていただき、利用者様の笑顔に支えられてきました。皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
しかしながら、ここ数ヶ月、体調が優れない日が続いており、このまま業務を続けることが難しいと感じるようになりました。
大変申し訳ございませんが、自身の健康を第一に考え、静養に専念させていただきたく存じます。
退職までの間、できる限りの業務を引き継ぎ、ご迷惑をおかけしないよう努めます。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。」
例文3:家庭の事情の場合
「施設長、いつもお世話になっております。私事で大変恐縮なのですが、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご相談させて頂きました。
在職中は、皆様に温かく支えていただき、本当に感謝しております。利用者様の生活をサポートできたことは、私にとって大きな喜びでした。
実は、〇〇(具体的な家庭の事情を簡潔に説明)があり、今後は家族との時間をより大切にしたいと考えております。
急なご報告となり大変恐縮ですが、退職までの間、責任を持って業務に取り組み、しっかりと引き継ぎをさせていただきます。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。」
後悔しない転職・再就職のために
退職はゴールではありません。新たなスタートラインに立つための準備期間です。
後悔しない転職・再就職をするために、以下のことをもう一度考えてみましょう。
自己分析をしっかり行う
なぜ退職したいと思ったのか、そもそもなぜこの職場を選んだのか、もう一度選んだ理由や退職になった経緯を思い返し、反省するところは反省していきましょう。
そして、次の職場では何を重視したいのか、同じような退職にならないかを頭の中でシミュレーションしてみましょう。
自分の行動を振り返り、シミュレーションを行うと、自分の強みや弱みが再認識できると思います。
自己分析をしっかり行い、自分への理解を深めることで、新しい職場での成功に近づくことができます。
情報収集を徹底する
福祉の施設は制度に縛られているせいもあって、どこの施設もほぼ同じような状態です。
また同じ退職という選択をしないためにも、情報収集は欠かせません。
転職サイトやエージェントを活用して、転職先の情報を仕入れましょう。
施設見学をして、施設の環境や雰囲気を感じることも非常に重要です。
口コミや評判を書いたサイトから情報を得るのも、ひとつの方法だと思います。
譲れない条件を明確にする
これは自己分析のところと同じような分析になりますが、次に就職する先でこれは絶対に譲れないという条件を洗い出します。
給与なのか、勤務時間なのか、それとも休日なのか、福利厚生なのか、職場の雰囲気なのか。
人それぞれこれだけは絶対に今より良くなってほしいと思う部分です。
これを明確にするだけで、再就職したあと後悔することは少なくなるでしょう。
面接対策をしっかり行う
再就職するためには、自分にとって最も適した施設に入らなければなりません。
せっかく相性の良い企業を見つけても、試験や面談で落ちてしまっては、また元の生活に戻ってしまいます。
次に就職する施設の面接対策は、必ず行うようにしましょう。
自分の経験やスキルを十分にアピールできるように練習して、面接にのぞみましょう。
退職後も学び続ける姿勢を持つ
退職というネガティブなことを経験しても、気持ちは学び続けるという前向きな姿勢を持ちましょう
退職後も勉強を続け、そのことを次の施設でもアピールできれば、次の施設にも良い印象を与えることができるでしょう。
また、再就職した後も、新しい環境で学び続けなければなりません。
新しい職員さんや、新しい利用者さんとの出会いがあり、制度もどんどん変わっていますので、学ぶことが終わることはありません。
自分の学びが多くの人に幸せをもたらすと考えて、学び続けましょう
まとめ
生活相談員の退職理由は人それぞれですが、決して珍しいことではありません。
大切なのは後悔のない決断をすること、そして円満に退職するための努力をすることです。
この記事の内容によって、あなたが新たな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
あなたの今後のキャリアが輝かしいものになるよう、心から応援しています。








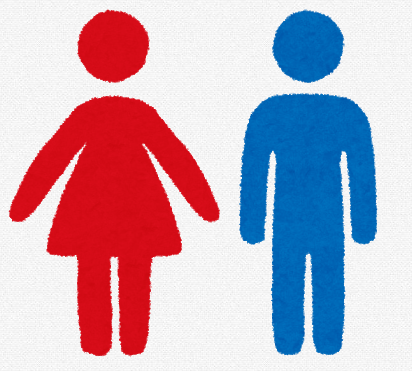


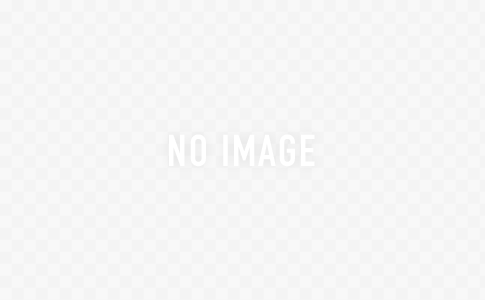

ショートステイ事業所に勤務していたAさんは、生活相談員としてショートステイの利用者やご家族と話しをしながら、利用者が安心して生活できるようにいろいろな関係機関と調整をしていました。そんな中、ある利用者がなかなか眠れないので、「眠れないときだけ眠前薬を飲ませたい」と思い、ご家族に頓服で処方してもらうように依頼しました。それを施設長が聞いて「眠らせる薬を家族に頼むとは何事か!」と怒ってきました。親切心で言ったつもりが、悪い方向に受け取られ、働く意欲がなくなった。こういった状況が2回、3回と続いたので転職を決意しました。