高齢者施設や福祉サービスを利用する際に、頼りになるはずの「生活相談員」。しかし、中には「偉そう」「態度が悪い」「正確が悪い」「上から目線」と感じてしまうような、横柄な態度の相談員もいるようです。
「親身になってくれると思ったのに…」「高圧的な態度で怖い…」
そんな経験をされた方、あるいは、これから福祉サービスを利用するにあたって不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、「偉そうな生活相談員」と感じてしまう背景や、その実態、そして、どのように対処すれば良いのかを、具体的なエピソードを交えながら、徹底的に解説します。
さらに、生活相談員との上手な付き合い方、良好な関係を築くためのヒントもご紹介します。
この記事を読むことで、生活相談員の態度に悩んでいる方の心が少しでも軽くなり、より良い福祉サービスを受けるための一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
1. なぜ「偉そうな生活相談員」と感じるのか?体験談から見る5つのパターン
「偉そう」と感じるかどうかは、個人の感じ方によるところが大きいものです。しかし、多くの人が「偉そう」と感じる生活相談員の言動には、いくつかの共通するパターンが見られます。
ここでは、実際に寄せられた体験談をもとに、5つのパターンに分類して解説します。
パターン1: 上から目線の発言
- 「そんなことも知らないんですか?」 と、利用者の知識不足を指摘するような言い方をする。
- 「こうするべきです」 と、一方的に決めつけるようなアドバイスをする。
- 専門用語を多用し、理解できない利用者に対して 「だから言ったじゃないですか」 と呆れたように言う。
パターン2:威圧的な態度・高圧的な物言い
- 目を合わせず、面倒くさそうに対応する。
- 腕組みをしながら話を聞く。
- 大きな声でまくしたてるように話す。
- 質問に対して、冷たくあしらうような返事をする。
「弟の障害者支援施設への入所について相談に行ったのですが、生活相談員の態度は、最初から威圧的でした。目を合わせようともせず、私の話を面倒くさそうに聞いていました。質問をしても、冷たく『それは無理です』『決まりですから』とだけ。まるで、私たちが悪いことをしているかのような扱いを受け、とても嫌な思いをしました。」
パターン3: 話を聞いてくれない・話を遮(さえぎ)る
- 相談者の話を最後まで聞かず、途中で遮って自分の意見を言う。
- 相談者が話している途中で、他の業務を始める。
- 相談内容とは関係のない話を始める。
「父の認知症が進み、施設への入所を考えていることを相談しました。しかし、生活相談員は私の話をろくに聞いてくれませんでした。私が話している途中で、何度も『それで、結局何が言いたいんですか?』と遮ってきたり、他の職員と話し始めたり…。話を聞いてもらえている感じが全くしませんでした。」
パターン4: 専門用語を多用してわかりにくい
- 介護保険制度や福祉サービスに関する専門用語を並べ、わかりやすく説明しない。
- 利用者や家族が理解できていない様子なのに、そのまま話を続ける。
- 質問しても、さらに専門用語で返答する。
「自分の施設入所について相談に行ったのですが、生活相談員の説明が全く理解できませんでした。難しい言葉ばかり並べられて、チンプンカンプンでした。何度か質問したのですが、『ですから、これは○○制度に基づいて…』と、さらに難しい言葉で説明されて、結局よくわかりませんでした。」
パターン5: 杓子定規な対応・融通が利かない
- 規則やマニュアルを盾に、柔軟な対応をしようとしない。
- 利用者の個別の事情を考慮せず、一律的な対応をする。
- 例外を認めず、相談者を困らせる。
「母の介護のことで、どうしてもイレギュラーな対応をお願いしたくて相談に行ったのですが、生活相談員は『規則ですから』の一点張り。こちらの事情を説明しても、『前例がありません』『規則で決まっています』と言うばかりで、全く融通が利きませんでした。もう少し、柔軟に対応してくれてもいいのに…と、悲しくなりました。」
これらのパターンは、あくまで一例です。しかし、多くの人が「偉そう」と感じる生活相談員の言動には、相手の立場や気持ちを考えない、一方的で配慮に欠けた対応という共通点が見えてきます。
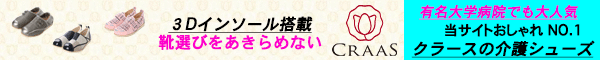
なぜ「偉そう」な態度をとるのか?生活相談員の事情と背景
では、なぜ一部の生活相談員は、利用者やその家族に対して「偉そう」な態度をとるのでしょうか?
そこには、生活相談員を取り巻く、様々な事情や背景が関係していると考えられます。
理由1:多忙によるストレスと疲れ
これは施設によって違いますが、全般的に生活相談員の業務範囲は広く、多忙を極めています。
私の経験上の話ですが、以下の仕事をしていました。
- 利用者との面談、ヒアリングシートの作成
- アセスメントと計画書の作成
- 利用日の調整やケアマネへの説明
- 契約書の作成、入所、退所の手続き
- 介護職員、看護職員の仕事の調整や利用者への対応方法の説明
- 主治医への連絡
- サービス担当者会議への出席
- 利用者が亡くなった時は、24時間いつでも施設に駆けつける
- 電球が切れたときの交換
- トイレがつまったときの対応
- 利用者の送迎業務
- 週間予定、年間予定の作成
- 請求書の作成、国保連請求のチェック
- 事業所の変更申請の書類作成と提出
- 36協定や労務管理の書類作成
- 利用者からのクレーム対応
- 介護保険制度の変更による、制度についての勉強
ざっと思い出しただけでもこれだけあります。
まだ他にもあるような気がしますが、とにかく範囲が広いです。
仕事の範囲が広くて業務量が多いため、常に時間に追われています。
このような状況になると、心身ともに疲れてしまい、ストレスを抱えこんでしまいます。
その結果一人ひとりに対して丁寧に対応する余裕がなくなり、無意識のうちに偉そうな態度をとってしまう可能性があるのです。
理由2:専門職としてのプライド
生活相談員になるためには、「社会福祉主事」「社会福祉士」「社会福祉施設に3年以上勤務」などの条件が必要になります。
つまり、福祉の専門職と言ってもいいと思います。
さらに施設の中で広い範囲の業務をこなしていると、当然ですが介護職員や一般の人よりも知識が豊富になってきます。
そうすると施設の中のだいたいのトラブルは、解決できるようになります。
そのため、専門職としてのプライドが高く、自分の知識や経験に自信が持てるようになります。
この自信が過剰になると、利用者や家族に対して「自分の方が専門知識がある」という意識が働き、無意識のうちに見下したり、上から目線になったリする可能性があります。
理由3:相談員の防衛としての態度
生活相談員の仕事は、利用者やその家族から、様々な相談を受けます。
中には、解決困難な問題や、理不尽な要求、厳しいクレームなど精神的に負担が大きい相談も少なくありません。
このような大きな負担を抱えたまま業務を続けると、自分を守るための防衛機制として、無意識のうちに偉そうな態度をとってしまうことがあります。
あえて「威圧的」な態度をとることで、相手からの攻撃を避け、自分の立場を守ろうとするのです。
全く悪気なく行われる行為ではありますが、この行為をされる側からすると「偉そう!」「何様?」という感情を抱いてしまいます。
理由4:コミュニケーション能力の不足
生活相談員にはコミュニケーション能力の優れた人が多いですが、全ての生活相談員が高いわけではありません。
コミュニケーション能力の低い人は、相手の気持ちを汲み取ったり、周囲の空気を読み取ったりすることができません。
そんな人が発する言葉というのは、威圧を感じてしまいます。
本人は偉そうにしているつもりがなくても、相手からは「上から目線」とか「威圧的」と受け取られてしまう可能性があります。
理由5:組織風土や教育体制の問題
生活相談員の態度には、所属する施設の組織風土や教育体制も影響します。
例えば、
- 職員同士のコミュニケーションが不足している
- 上司が生活相談員に対して高圧的な態度をとっている。
- 職員に対する教育が不十分である(お客さんに対するマナー研修をやっていない)
そういった環境では、生活相談員の態度が偉そうになってしまうリスクが高くなります。
このような事情はあくまで偉そうな態度をとってしまう背景の一例です。もちろん全ての相談員がこのような背景を持っているわけではありません。
しかし、生活相談員を取り巻く厳しい労働環境や、専門職としてのプレッシャーなどが偉そうな態度を生み出す一因となっていることは知っておく必要があるでしょう。
「偉そうな生活相談員」への対処法:5つのステップ
「偉そうな生活相談員」に遭遇してしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
ここでは、試していただきたい5つのステップに分けて解説します。
もしこのブログを生活相談員さんが読まれているのであれば、上記のことに十分気をつけていきましょう。
ステップ1:冷静になりましょう
まずは、深呼吸をして冷静になりましょう
感情的になってしまうと、相手との関係が悪化し、問題解決が難しくなります。
ステップ2:相手の立場を理解しようと努める
前述したように、生活相談員が偉そうな態度をとる背景には、様々な事情があります
相手の立場や状況を理解しようと努めることで、過剰に反応せずに済む場合があります。
ステップ3:共通の目標に立ち戻る
お互いに共通している目標が必ずあるはずなので、そこに立ち戻って、お互いに確認しあうと建設的な話に繋がりやすいです。
例えば、「入所者には安心して過ごしてもらいたいですよね」とか「事故なく楽しく過ごしてもらいたいですよね」等お互いの立場を考えれば、共通点が必ずあるはずです。
そこに立ち戻って話をすれば、生活相談員も受け入れやすくなります。
ステップ4:自分の要望を明確に伝える
自分が何を求めているのか、どのような対応を希望するのかを、具体的に伝えましょう。曖昧な表現では、相手に気持ちが伝わらず、相談員さんに意見が届かない場合があります。
例えば「もう少し詳しく説明してほしい」「私の話を最後まで聞いてほしい」「○○の件で困っているので、解決策w一緒に考えてほしい」など、具体的かつ明確に伝えることが重要です。
ステップ5:記録を取る
相談内容や相手の言動を、できるだけ詳細に記録しておきましょう。メモを取ったり、可能であれば録音したりするのも有効です。
記録は、後で問題が大きくなった場合に、証拠としてやくだちます。
状況が改善しない場合
上記のステップを試しても状況が改善しない場合は、生活相談員の上司や、施設の相談窓口、あるいは、地域の福祉サービス苦情解決期間などに相談しましょう。
一人で抱え込まず、第三者に介入してもらうことで、問題解決の糸口が見つかる可能性があります。
相談窓口の例
- 施設内の相談窓口
- 市区町村の介護保険課や障害福祉課
- 地域包括支援センター
- 運営適正化委員会連合会
- 国民健康保険団体連合会
これらの機関では、福祉サービスに関する苦情や相談を受け付けています。
こういった相談期間に話をもちかけると、必ずそこの施設に指導が入りますので、まずは相談をしてみましょう。
生活相談員と良好な関係を築くためのヒント
生活相談員と良好な関係を築くことは、より良い福祉サービスを受ける上非常に重要です。
ここでは生活相談員お上手に付き合うためのヒントをご紹介します。
ヒント1:感謝の気持ちを伝える
生活相談員は、多くの業務を抱え日々奮闘しています。
そんな忙しい中で、面倒なことが増えると当然不機嫌になりますし、偉そうな態度をとってしまいます。
ところが「いつもお世話になっております」というように、感謝していることを全面に出して話をすると、良好が関係を築くことができます。
ヒント2:相手の立場や状況を理解する
生活相談員が多忙であることや、様々な制約の中で業務を行っているんだ、ということを理解しましょう。
相手の立場や状況を理解することで、多少の不備があっても、寛容な気持ちで接することができ、不要な争いを避けることができるでしょう。
ヒント3:積極的にコミュニケーションを取る
日頃から、積極的にコミュニケーションを取るように心がけましょう。
挨拶をする、世間話をするなど、些細なやりとりを積み重ねることで、信頼県警が築きやすくなります。
お互いに認め合った仲になると、いきなり横柄な態度をとられることはまずありません。
ヒント4:質問や要望は具体的に
質問や要望がある場合は、具体的かつ明確に伝えるようにしましょう。あいまいな表現では真意が伝わらず、誤解を生む可能性があります。
ヒント5:相手を尊重する
生活相談員さんが恐れていることはたくさんあるのですが、その仲で、「利用者やお客さんから、みとめられてない」というのを感じたときに、とても恐怖を感じます。
そんな恐怖を感じてしまうと、なかなか利用者やご家族と積極的にコミュニケーションを取ろうとは思わなくなります。
生活相談員さんを尊重すれば、相手も心を開いて、多くの情報を提供してくれるはずです。
まとめ:建設的なコミュニケーションで、より良い福祉サービスを
「偉そうな生活相談員」と感じてしまう背景には、利用者側の感じ方の問題だけではなく、生活相談員を取り巻く環境や、業務上の課題など、様々な要因が複雑に絡み合っています。
大切なのは、一方的に相手を責めるのではなく、相手の立場や状況を理解しようと努め、建設的な意見を出して、問題解決を図ることです。
この記事で紹介した対処法やヒントを参考に、生活相談員と良好な関係を築き、より良い福祉サービスを受けていただければ幸いです。
また、偉そうにしている相談員さんは介護職員さんに対しても偉そうにしていることが、多分にあります。
生活相談員が介護職員さん偉そうにするのは今の時代あまりいいとは言えません。それが原因で介護現場の職員が不足してしまっては元も子もありません。
現場が不足して生活相談員が介助を手伝うようになってしまうと、ただでさえ忙しい生活相談員の仕事がさらに増えてしまいます。
お互いがお互いの業務を尊重できるように、日々の業務をこなしていきましょう。








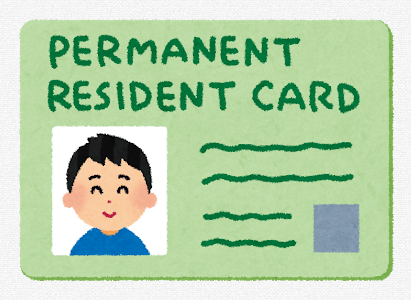
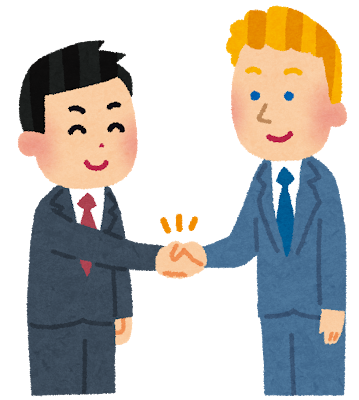
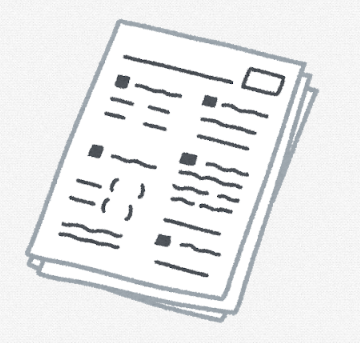
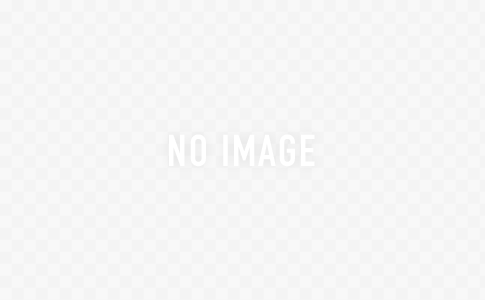
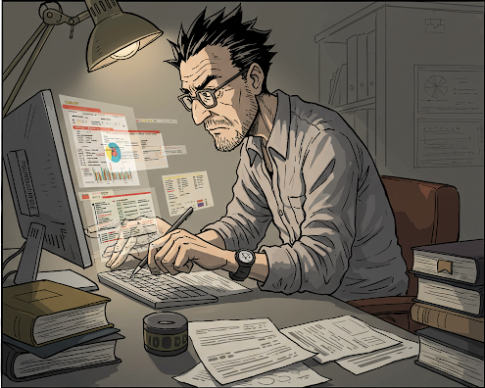
「母の介護のことで相談に行ったのですが、担当の生活相談員は、私の話をあまり聞かずに、一方的に話を進めました。『デイサービスを利用するべきです』『ショートステイも検討してください』と、こちらの事情もよく聞かずに決めつけるような言い方で、とても不快でした。『そんなことも知らないんですか?』と言われた時は、本当に傷つきました。」