生活相談員を長くやっていて思いますが、生活相談員はストレスの多い職種です。
慣れてしまえば、そんなに負担には感じませんが、上司や介護士、利用者、家族などと関わるため、それぞれの思いを実現していく必要があります。
生活相談員はストレスに強くならなければ、いい仕事はできません。
それぞれにどんな思いがあるかをここで紹介していきたいと思います。
上司からもらうストレス
上司から言われることは、だいたい決まっています。
「利用者を増やせ、ベッドを埋めろ」です
空きベッドをとにかく減らすように言われます。
営業して、利用者を増やしたり、ベッドを埋めることが好きな人は、ストレスは感じないと思いますが、私はストレスでした。
介護士からもらうストレス
介護士さんから言われることは、たくさんあります。
私がストレスを感じていたのが、介護士同士の意見の違いです。
A介護士は「怪我をさせないように、車椅子で食堂に行く」
B介護士は「本人はまだ歩けるのだから、少しでも歩いて食堂に行く」
このように全く反対の対応になることがあります。
そこで介護士同士の対立があります。
考えの違いがあって、どちらも正しいし、どちらも間違ってないから、対応が難しいです。
考えが違うだけならいいのですが、対応方法を必ず決めなければいけないので、相談員からすると、かなりストレスになります。
利用者からもらうストレス
利用者からは、私はあまりストレスをもらいませんが、利用者によっては、ちょっとストレスをもらいます。
男性の利用者で、「お前は施設の職員か。お前この仕事向かないすぐに辞めろ」と言われたりすると、へこみます。
他にも、ずっと叫んでいる利用者の対応とかも、介護士も生活相談員も困ります。
差別的な発言になりますが、特に男性の利用者は、特徴がありすぎて、ストレスになることがあります。
家族からもらうストレス
家族さんはみんないい方ばかりです。
8割から9割の家族はとてもいい家族で、施設や介護士さんに対して、とても協力的です。
私も家族の方に何度も助けられたことがあります。
ところが、家族によっては、自分の身内を大事にして欲しいとすごく訴えて来られる家族がいます。
「うちの親にだけ、こんな対応をして欲しい」とか
「うちの親だけ、食事はいいものを出して欲しい」
といった、自分の身内だけ特別対応をして欲しいと言われる家族がいます。
施設側もできるだけ、利用者のためにサービスを提供しようとしていますが、この人だけ特別に、というのはなかなか難しいのが現状です。
外出の機会や、イベントの参加や、環境の整備に関しても、1人の利用者に集中しないように、平等になるように心がけています。
そんな施設の取り組みの中で、この人だけ特別にしないといけないというのは、非常にストレスを抱えます
まとめ
生活相談員が、いろいろな人と関わりながら、仕事を続けているというのが、上記で分かると思います。
上司や介護士、家族や利用者などなどから、ストレスを感じながら仕事をしています。
私が働いていて、一番感じていたのが、上司ですね。
上司の理解があるのと、理解が全くないのとでは、モチベーションに大きな違いが出てきます。
上司がしっかり自分のことを見てくれてるという実感があると、他のストレスはどうにかなるものです。
上司を選ぶことはなかなかできないことですが、せめて自分が上司になった時は、しっかり下の人を見てあげる上司になってください。
これから生活相談員を目指す方や、今生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います。



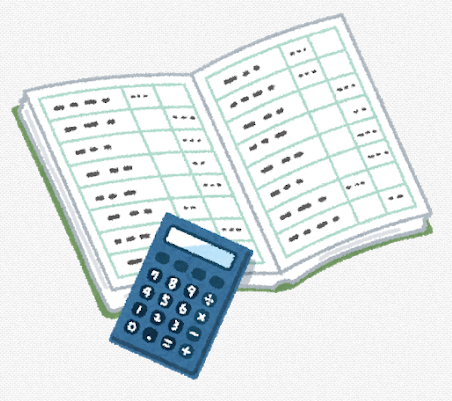

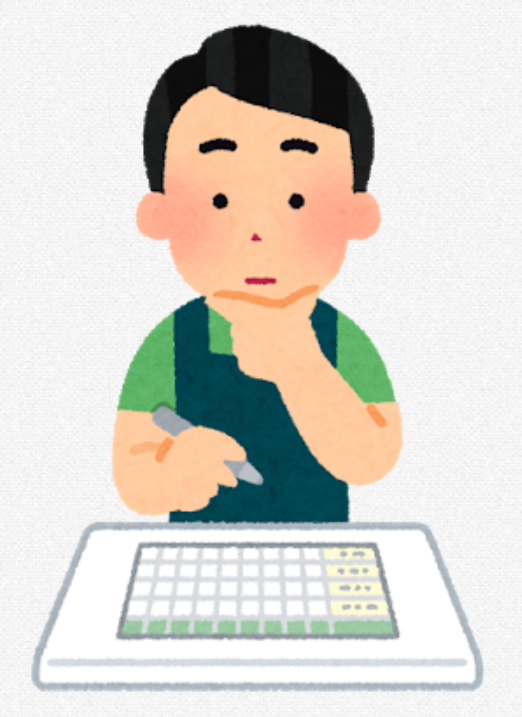


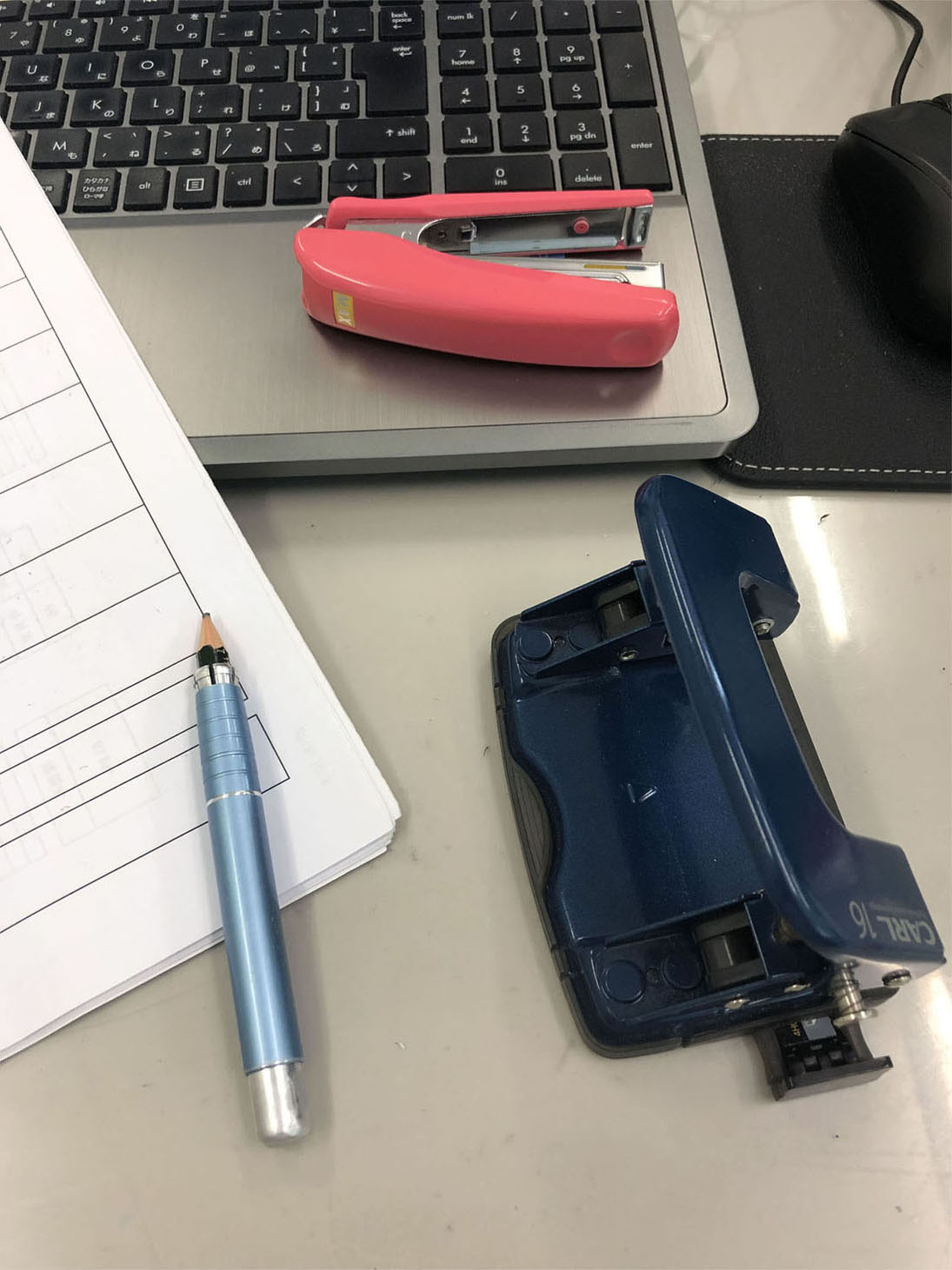


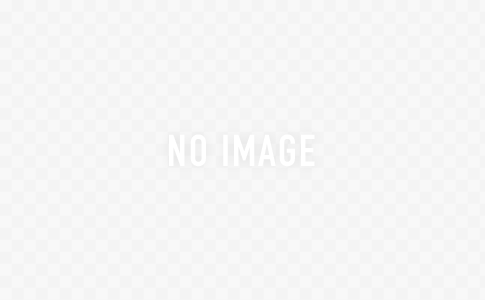
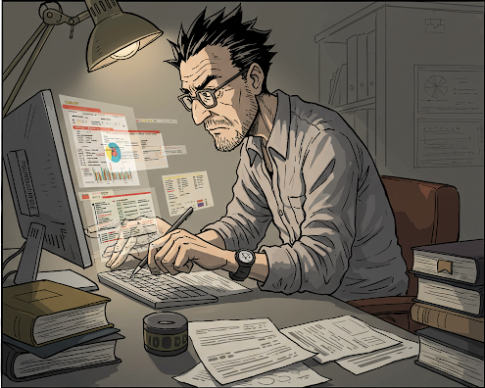
コメントを残す